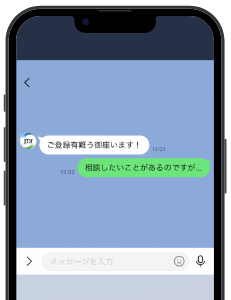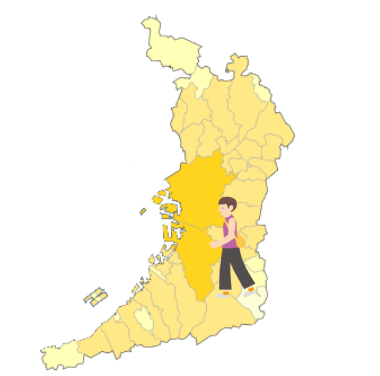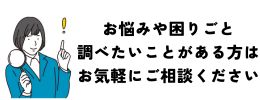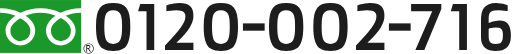従業員が労災保険料を不正受給していないか確かめる方法
更新日:2025-08-29
掲載日:2025-08-29

労災保険料の不正受給は、企業にとって見過ごせない問題です。従業員が不正に給付を受けていると、会社の資金負担が増えるだけでなく、職場全体の士気や信頼関係にも影響を及ぼしかねません。特に、早い段階で事実を確認し、適切に対処することが企業を守るために不可欠です。本記事では、労災保険料の不正受給の実態を整理するとともに、受給中の従業員の様子をどのように確認すべきかについて詳しく解説します。
労災保険料の不正受給を確認する方法とは
労災保険料の「不正受給」問題
労災保険制度の実態
労災保険は、本来、労働者が業務中や通勤途中に負ったケガや病気に対して、治療費や休業補償を行い、生活の安定を支えるための制度です。しかし、その趣旨を逆手に取り、実際には労災に該当しないケースで給付を受けようとする不正受給が問題となっています。例えば、私生活でのケガを「業務中の事故」と偽るケースや、治療が不要なのに長期間通院を装うケースなどが見られます。
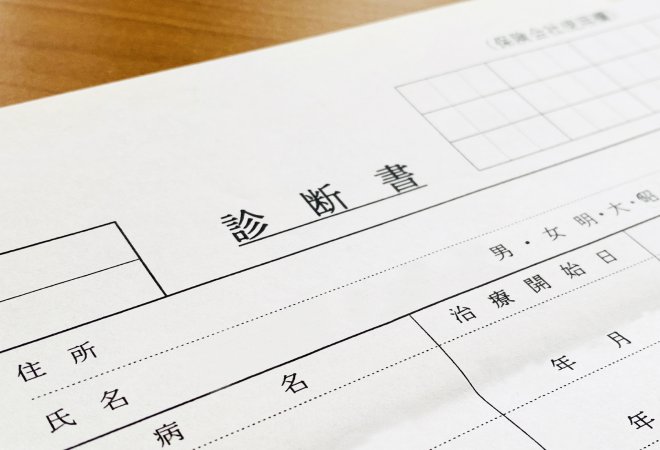
不正受給の典型的な手口とは?
不正受給にはいくつかのパターンがあります。もっとも多いのは、発生状況を偽装するケースです。私用中の事故を「勤務中の労災」として申告したり、通勤経路外での事故を「通勤災害」として処理するケースが典型です。また、医師へ虚偽の申告をして診断書を作成したり、すでに治癒しているのに休業を続けて給付を得るケースも少なくありません。これらは企業に対する背信行為であり、労災保険制度そのものの信頼を損なう深刻な問題です。
不正受給が企業に与える影響
従業員の不正受給は、単なる金銭的損害にとどまりません。発覚した場合、企業の管理体制が問われ、労務管理やコンプライアンス面で指摘を受ける可能性があります。さらに、不正を放置すると職場全体のモラルが低下し、他の従業員の士気や信頼関係にも悪影響を及ぼします。結果として、会社の社会的信用が損なわれ、取引先や顧客との関係に支障が出る恐れもあるのです。
労災保険料を不正受給している従業員への処分とは?
経済的な処分
労災保険を不正に受給した従業員には、不正に得た給付金の全額返還が命じられ、さらに追加の納付を課される場合もあります。これにより従業員本人に大きな経済的負担が生じるだけでなく、返還や納付を怠れば財産差押えといった強制手続きに発展する可能性もあります。企業としては、従業員による不正が発覚した際には迅速に把握し、適切に対応することが求められます。
法的な処分
不正受給が悪質であると判断された場合、従業員は刑事事件として詐欺罪などに問われる可能性があります。刑事責任が問われれば前科がつくことになり、社会的信用の喪失は避けられません。事業者にとっても、従業員の不正が社内コンプライアンス体制の不備として見られ、企業イメージの低下につながる恐れがあります。そのため、従業員による不正を早期に発見し、適切に対応することが重要です。
労災保険料の不正受給を放置した場合のリスク
会社の経済的損失
従業員による労災保険の不正受給を見逃すと、会社に不必要な経済的損失が発生します。調査機関から管理責任を問われ、返還や罰則に対応するためのコストが増加するほか、コンプライアンス体制の見直しや再発防止策の実施にも費用を割かざるを得ません。こうした対応費用は本来の事業運営に直接的な影響を与え、経営の健全性を損なうリスクにつながります。
会社の人的損失
不正受給を放置すると、従業員の規律やモラルが大きく損なわれます。会社が不正を黙認していると見なされれば、他の従業員の働く意欲や忠誠心にも悪影響を及ぼし、組織全体の生産性が低下しかねません。さらに、内部の統制力が弱まることで、今後の不正行為を助長する土壌を生んでしまう危険性もあり、健全な職場環境の維持が難しくなります。
会社の信頼への影響
従業員による労災保険料の不正受給が発覚すれば、企業そのものの信頼性が大きく損なわれます。取引先や顧客から「管理体制に問題がある会社」と見なされ、契約の打ち切りや新規取引の難航といった事態を招きかねません。また、企業イメージが低下することで採用活動や人材定着にも悪影響を及ぼし、長期的な競争力の低下につながるリスクがあります。
労災保険料の不正受給を確認する方法
社内での様子を確認
従業員が労災を理由に休業している場合、まずは社内で普段の様子を確認することが重要です。所属部署や同僚からの聞き取りを通じて、業務態度や行動に不自然な点がないかを把握します。また、申告された労災の内容と実際の行動や勤務態度に食い違いがないかを確認することも有効です。社内の状況を整理しておくことで、不正受給の兆候を早期に発見する手がかりとなります。
社外での様子の確認
従業員が労災で休業している場合、社外での行動にも注意が必要です。本当に療養や通院を続けているのか、それとも遊興や副業に従事しているのかを見極めることで、不正の有無を把握できます。また、労災の内容に見合わない行動をしていないかを確認することも欠かせません。社外での様子を知ることは、社内の情報だけでは把握できない実態を明らかにするうえで重要な視点となります。

自社で調査する際のリスク
会社が独自に従業員の不正受給を調査しようとすると、重大なリスクを伴います。従業員に調査の事実を気づかれてしまえば、社内の信頼関係が崩れるだけでなく、プライバシー侵害や違法行為に発展する恐れがあります。さらに、会社側が集めた情報が証拠として不十分であれば、不正を立証できないばかりか、逆に従業員から訴えを起こされるリスクも否定できません。正確で法的に有効な証拠を得るためには、慎重に進めることが求められます。
労災保険料の不正受給を確かめる探偵調査
不正を裏付ける証拠が重要
従業員による労災保険料の不正受給を確実に立証するには、客観的かつ法的に有効な証拠が欠かせません。単なる疑いや社内の噂では、会社が適切な対応を取ることは難しく、逆に従業員とのトラブルを招く恐れもあります。例えば、就業規則に基づいた処分や法的手続きを進める場合にも、証拠の有無が結果を左右します。会社のリスクを最小限に抑えるためには、不正の事実を裏付ける信頼性の高い証拠を収集しておくことが重要です。
従業員の不正受給を確かめる探偵調査
従業員の不正受給に疑いがある場合、探偵による行動調査が有効な手段となります。探偵は従業員の行動や勤務外での様子を客観的に把握し、療養や休業の実態と申告内容が一致しているかを明らかにできます。また、社内では得られない外部での情報収集や、法的手続きに耐えうる証拠の整理も可能です。自社での調査ではリスクが伴いますが、探偵を利用することで安全かつ効率的に事実確認が進められ、問題解決に向けた判断材料を確保できます。
行動調査とは?
行動調査とは、対象となる従業員が実際にどのような生活を送っているのかを確認するために、探偵が尾行や張り込みを行い、行動の様子を写真や動画で記録する調査です。労災の申告内容と行動が一致していない点がないか、客観的な証拠をもとに証拠を明らかにできます。社内で目が届かない場面でも把握できる点が大きな特徴であり、労災保険料の不正受給を立証する上で有効な手段となります。
労災保険料の不正受給調査に関するよくある質問と回答
Q.不正受給の調査にかかる日数の目安を教えてください
A.労災の状況や確認したい内容によって調査期間は変動します。数日の調査で十分な場合もあれば、通勤時の様子や休日の行動など多角的な証拠が必要なケースでは、数週間に及ぶこともあります。調査の目的と必要な精度に応じて、柔軟に期間を調整することが可能です。
Q.他の社員に調査していると知られたくありませんが可能でしょうか?
A.探偵による調査は、対象者本人はもちろん、他の社員に気づかれないよう徹底した配慮のもとで行われます。尾行や張り込みも目立たないように実施され、社内に情報が漏れる心配はありません。依頼主である会社の立場を守りつつ、客観的な証拠を収集することができます。
Q.受給中の社員は遠方の実家で療養中だそうですが調査は可能ですか?
A.はい、可能です。調査エリアに制限はなく、遠方であっても対象者の生活状況や行動を確認することができます。実家で静養している様子が申告通りか、または不自然な行動が見られないかを、現地での調査を通じて確認します。場所に関わらず必要な証拠を確保できる点が探偵調査の強みです。
労災保険料の不正受給のお悩みは探偵に相談
従業員の労災保険料に不正受給の疑いがある場合は、まずは24時間対応の無料相談窓口をご利用ください。不正受給の問題は、事実を確かめずに放置すると経済的損失や信用問題に直結し、会社に大きな負担をもたらします。「申告と実際の行動が違う気がする」「証拠を確実に押さえたい」といった不安を抱えている企業担当者の方は、専門家に相談することで解決への糸口が見つかります。一人で悩むよりも、まずは相談から始めてみることが重要です。
※当サイトのご相談事例は、探偵業法第十条に基づいて、個人が特定されないよう内容を一部編集しています。 弊社は関西という地域柄発生する様々な問題に対して、ご相談者様のプライバシーを最優先に考え、安心してご利用いただける調査サービスの提供を行っています。

一人で悩まず、
いつでもご相談ください。
ご相談・お問い合わせ
無料相談ダイヤル(24時間受付)
 0120-002-716
0120-002-716
ご相談や悩み事、誰にも言えない不安など、経験豊富なカウンセラーが真摯に対応させて頂きます。 どんな些細なことでも、一人で悩みを抱えずにご相談ください。

メール無料相談(24時間受付)
※ご相談・お見積もりは何度でも無料です。
※相談内容・プライバシーをお守りします。
※送信後48時間以内に返答がない場合はお電話でお問い合わせください。
※お急ぎの方は無料相談ダイヤル(0120-002-716)をご利用ください。
探偵法人大阪調査士会
大阪府大阪市北区西天満4丁目10-23 601
大阪府公安委員会 62240024号